小学校の通知表における3段階評価の割合は?「よくできる」は何個が平均?
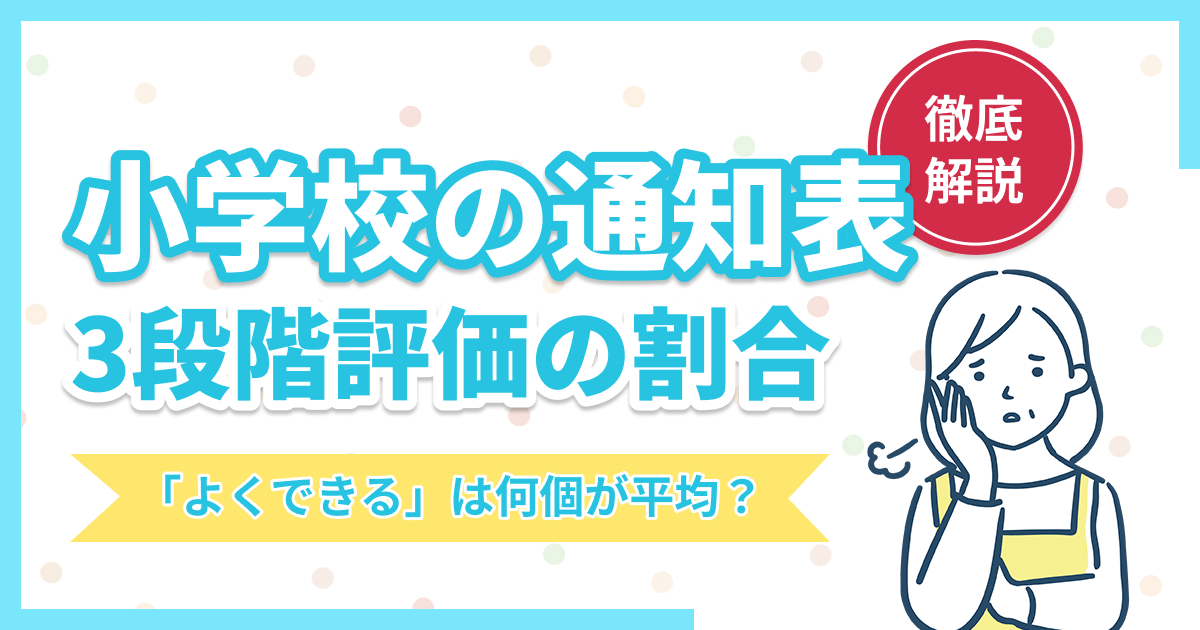
小学校の通知表評価は3段階ですが、最も上の評価である「よくできる」が少ないことで不安をお持ちではありませんか?
そこで本記事では、小学校の通知表3段階評価における割合の目安を解説します。
結論からいえば、「よくできる」が少ないこと自体は必ずしも問題ではありません。
一方で、「もう少し」が多い場合は対策が必要になります。
通知表の「よくできる」評価の割合が平均より多いのか少ないのか気になっている方は、ぜひ参考にしてください。
【前提】小学校の通知表の評価基準は”絶対評価”なので割合は決まっていない
まず前提として、小学校の通知表の評価基準は「絶対評価」なので、各評価における人数の割合は決まっていません。
2020年の学習指導要領改訂に伴うもので、昔のように各評価をつけられる人数が決まっている方式ではなく、子ども一人ひとりが学習目標をどれだけ達成したかに基づいて評価する方式に変わっています。
逆にいえば、人それぞれ評価が異なるため「よくできる」が何個といった平均はあまりあてにならないということです。
文部科学省から発布されている新しい学習指導要領の内容は以下を参考にしてください。
「よくできる」は平均で何個くらいもらうもの?
「よくできる(◎)」は平均で何個くらいもらうものなのか、気になる方もいるかもしれませんが、学校によって大きく差があり、一概に何個とは言えません。
ただし、評価項目が合計20項目あれば、約20%が◎という前述の割合から計算すると、平均4個前後がひとつの目安となります。
とはいえ◎がゼロの子も珍しくなく、10個以上の◎を取る子もいます。
学年や時期によっても変動するため、◎の絶対数で一喜一憂するよりも、お子さん自身の◎の数を前回の通知表や得意分野と比較して増減を見ていくことが大切です。
通知表の「よくできる」を増やすなら、完全個別指導のオンライン塾を利用するのが近道です。その中でも、テレビCMでもお馴染みのトライは、小学生の成績アップに特化したコースもあります。
小学生のお子さんが成績を伸ばすには、まずは学習習慣の定着が最優先です。小学生向けの学習基礎固めコースでは、学ぶ楽しさを講師が伝え続けることで、お子さんが自発的に毎日机に向かうようになり、無理せず自然と成績アップに繋がります。
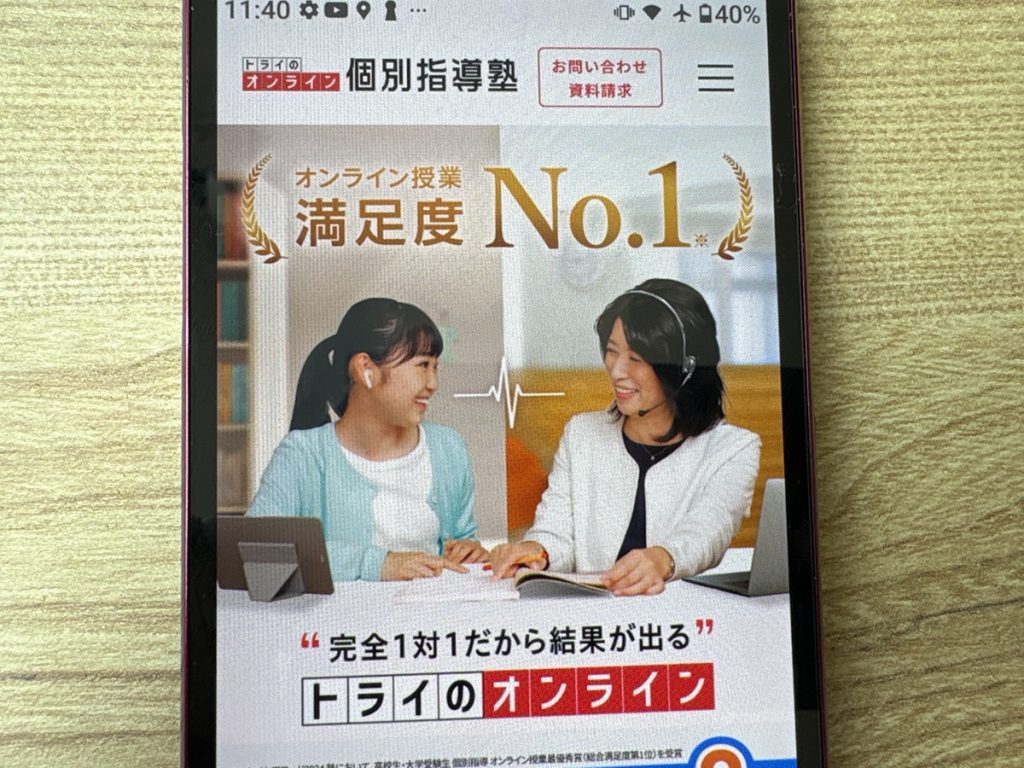
無料体験を受けると一人一人に合わせた学習プランを教育プランナーがご提案します。ご契約後は、毎回同じ家庭教師がお子さんの理解度のペースや苦手分野、得意に合わせて、丁寧に指導。次の通知表をもらうまでに、成績が見違えるようにアップすることは間違いありません。
また、オンラインによる無料の学習相談で、Amazonギフト券などのデジタルギフト500円分がもらえます。
資料請求・見積もり・体験授業はこちら
トライのオンライン個別指導塾 公式サイト無料相談で500円分のデジタルギフトが貰える
小学校の通知表3段階評価の割合の目安
小学校の通知表3段階評価の割合の目安を、評価ごとに解説します。
- ◎(A)=「よくできる」
- ○(B)=「できる」
- △(C)=「もう少し」
前述の通り、現在の通知表評価は絶対評価なため、よくできるの数はあくまで目安程度にとらえてください。
◎(A)=「よくできる」
「よくできる」は、「◎」や、「A」などと表現されることもあり、その学年の目標を十分に達成している状態を指します。
習熟度や正答率がおよそ80%~90%以上で、期待以上によくできている子どもにつけられる評価です。
割合は全体の約1割~2割程度と言われており、たとえば一つの評価項目(単元や観点)に対し、クラス30人なら「よくできる」は5人~6人前後というイメージです。
ただし、絶対評価のため、クラスの大半が高い習熟度だとより多くの生徒が獲得したり、反対に習熟度が全体的に低い場合は「よくできる」の割合も低くなったりします。
○(B)=「できる」
「〇」や「B」はクラスの約60%~80%と大半の生徒につけられる評価です。
学年の目標を概ね達成している状態のことで、標準的な理解度なので必要な内容はしっかり身についています。
ただし、「できる」が該当する範囲は広く、中学生の5段階評価でいえば、4~2相当です。
4や3寄りなら問題ありませんが、2寄りの場合は学習サポートを検討した方がよいでしょう。
△(C)=「もう少し」(がんばりましょう)
「もう少し」は、「△」や「C」、「がんばりましょう」といった評価を指す場合もあります。
対象者は0~20%程度と一部で、1教科につきクラスで数人程度に留まることが多いです。
「もう少し」は学習に明らかなつまずきが見られる場合が多く、現時点では十分ではないので、今後の学習で補っていく必要があります。
ただし、得意不得意もあるため、「もう少し」と評価されたからといって落ち込むことはありません。
つまずきを解消するために適切に学習サポートを行うことで、「できる」や「よくできる」に伸ばすことは可能です。
小学校の通知表の評価の観点
小学校の通知表評価は、以下の3つの観点で行われます。
- 知識・技能
- 思考・判断・表現
- 主体的に学習に取り組む態度
学力だけでなく、主体性や思考能力など、総合的に評価されます。
ただし、教師・学校によって評価で重視するポイントは少しずつ異なります。
文科省による教員へのアンケート調査で、具体的にどこが評価されるのかを解説するので参考にしてください。
知識・技能
平成29年度に行われた学習指導と学習評価に対する意識調査報告書によれば、知識・技能の観点では「単元の区切りなどで実施する、業者作成のテストやワークシート」いわゆるテストの点数が重視される傾向にあります。
アンケート結果では、84.9%の教員がテストの点数が「知識・技能」の評価点に影響を及ぼすと回答しています。
また、その他には授業態度などの一般的な内容以外に、作文や作品、体育や図工における技や作品が影響を及ぼすという回答です。
円滑に評価を決定できているかの調査についても、「知識・技能」については「そう思う」と回答が1.4ポイントと多くなっており、定量的で評価しやすいのが理由と予想されます。
参考元:平成 29 年度 学習指導と学習評価に対する意識調査報告書
思考・判断・表現
「思考・判断・表現」については、テストの評点以外に「児童生徒が調べたことや考えたことについて、記述したレポートや作文、発表」が重視されています。
テストが影響を及ぼすという回答が74.0%に対し、レポートや作文などは76.0%と高い数値です。
また、評価を円滑にできているかの傾向として、約1.0ポイントと「知識・技能」に比べると難しさを感じている方もいるようでした。
参考元:平成 29 年度 学習指導と学習評価に対する意識調査報告書
主体的に学習に取り組む態度
「主体的に学習に取り組む態度」の観点では、「授業における教員の発問に対する反応等の観察」が73.9%と、最も重視される傾向にあります。
それ以外にも、レポートや発表が71.0%、児童生徒が記述したノートが71.7%と、取り組み態度全般が重視されています。
一方で、定量で測りにくい項目であるため、テストによる影響は21.2%と少なめです。
円滑な評価の実施状況についても0.6ポイントと、最も評価が難しい項目であることがわかります
参考元:平成 29 年度 学習指導と学習評価に対する意識調査報告書
小学校の通知表で「よくできる」がゼロ・少ないときはどうする?
小学校の通知表で「よくできる」が無かったり、少なかったりといったときはどうするのがよいのでしょうか。
まずは、以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。
- 「少ない=問題」ではない
- 原因を探る
- 対策を考える
- サポートを利用する
「よくできる」が少なくて気になるという方は、ぜひ上からチェックしてみてください。
「少ない=問題」ではない
前提として「よくできる」の数が少ない自体は、必ずしも問題ではありません。
「よくできる」の数の増減によって、子どもの得意分野や苦手分野が見えてきます。
また、「よくできる」は特筆して優秀な項目のみつけられるため、「できる」であればさほど気にする必要はないでしょう。
重要なのは、通知表評価を見て何が得意で何が不得意なのかを確認し、得意分野を伸ばしたり不得意分野の対策をしたりすることです。
まずは原因を探る
「よくできる」が少ない原因を探りましょう。
たとえば、以下のような内容に思い当たるものはないでしょうか。
- 提出物や授業態度の問題
- 本人の得意不得意
- 先生の評価基準
教員や学校ごとにも評価基準のブレはあるため、ある程度仕方ないと割り切ることも必要です。
提出物や授業態度、テストの点数など、対策できそうな部分から行います。
教師によって評価の基準が異なるのは本当?
文部科学省調査によれば、「評価規準の改善,評価方法の研究などは,教員個人に任されている」と回答した小学校教員は約25%です。
全体の4分の1程度は学校全体で評価方法を共有せず、教員個人に任されています。
逆にいえば、4分の3はある程度学校内で評価基準を共有しながら評価を行っているようです。
結論としては「学校や教員による」ということにはなりますが、参考にしてください。
参考元:平成 29 年度 学習指導と学習評価に対する意識調査報告書
子どもと対策を考える
「よくできる」が少ない原因に仮説を立てたら、対策方法を子どもと一緒に考えましょう。
「よくできる」が少ないことを責めるのではなく、「増やせるようにがんばろう」などとあくまでポジティブに声かけを行います。
一緒にどうするべきか考えることで、子どもも自分ごととしてとらえることが可能です。
家庭で自習の時間を決めるなど、無理なく対策を行ってください。
必要に応じてサポートを利用する
学習のさせ方が分からない場合や、親自身が教えられない場合、通信教育や家庭教師などの選択肢もあります。
テスト対策から中学校受験対策まで、目的に合わせて選択しましょう。
事前のヒアリングなどがある場合は、通知の「よくできる」を増やしたいなど具体的に目標を伝えるのもおすすめです。
小学校の通知表でオール「よくできる」(オール3)は可能?
そもそも小学校の通知表でオール「よくできる」(オール3)は可能なのか解説します。
- オール◎はレアケース
- 上位層の子は別の目標設定を
結論としてはかなり難しく、そもそもオール◎をつけることに学校や教員側が抵抗を持つ可能性があります。
オール◎はとてもレアケース
小学校の通知表で全ての評価項目が「よくできる」になるケースはほとんどなく、非常にレアケースです。
通知表は子どもの成長を促す意味合いもあるため、「全て◎だと改善点が見えず指導につながらない」という考えも教師が持っている場合があります。
すべて「よくできる」だと、次に何をするかがかえって設定しにくくなるためです。
テストの評点ですべてが決まるような場合であればまだしも、授業態度や意欲の部分などすべての項目で◎になるのは難しいと考えてください。
上位層の子は別の目標設定を
オール◎にするために無理な勉強をさせたり、プレッシャーを与えすぎたりすると、肝心のお子さんの学ぶ意欲や好奇心を損なってしまいかねません。
中学受験を視野に入れて難易度の高い問題集に挑戦してみる、得意科目をさらに極めてコンテストに出てみるなど、別分野の目標を立てて取り組むのがおすすめです。
オール◎を目指せるような子ども自体が稀というのもありますが、別の目標設定を行うことを検討しましょう。
小学生の通知表を上げる方法
小学生の通知表を上げる方法ついて、以下の3点を解説します。
- 苦手分野の洗い出しと計画立て
- 家庭学習の習慣づけ
- 通信教育を活用
計画を立てて対策を繰り返し行っていくことで、通知表の評価向上につなげられます。
学習サポートに不安がある方は、通信教育などの利用を検討しましょう。
「△」は必ず対応すべき!苦手分野の洗い出しと計画立て
覚えておきたいポイントとして、「もう少し(△)」がある場合は対応した方がよいでしょう。
教員の立場で考えると、クレーム対応などは避けたいので、具体的に説明できる原因がないと△はつけづらいと想定されます。
逆に△がある場合、目に見えて改善の余地があるということです。
苦手分野を洗い出し、苦手克服のための計画立てを行いましょう。
面談などがある場合は△になった理由などを訊いておくと、対策を立てやすくなるはずです。
家庭学習の習慣づけ
苦手分野の洗い出しと計画立てが終わったら、家庭学習を継続できるよう習慣づけを行ってください。
小学生、とくに低学年のうちは、毎日学習習慣をつけることが大切です。
机に向かって学習する習慣が身につけば、毎日自然とできるようになるため、まずは時間を決めて学習してみましょう。
通信教育を活用する
学習方法や、どう進めればよいのかわからないという方は、通信教育の活用も検討します。
小学生でも無理なく勉強できるさまざまなカリキュラムがあるため、自身に合った講座を探してみてください。
1コマ〇〇円から、月額〇〇円まで料金体系もさまざまで、紙の教材やWeb教材など学習スタイルも選択できます。
小学生が楽しみながら学習習慣をつけるなら進研ゼミがおすすめ
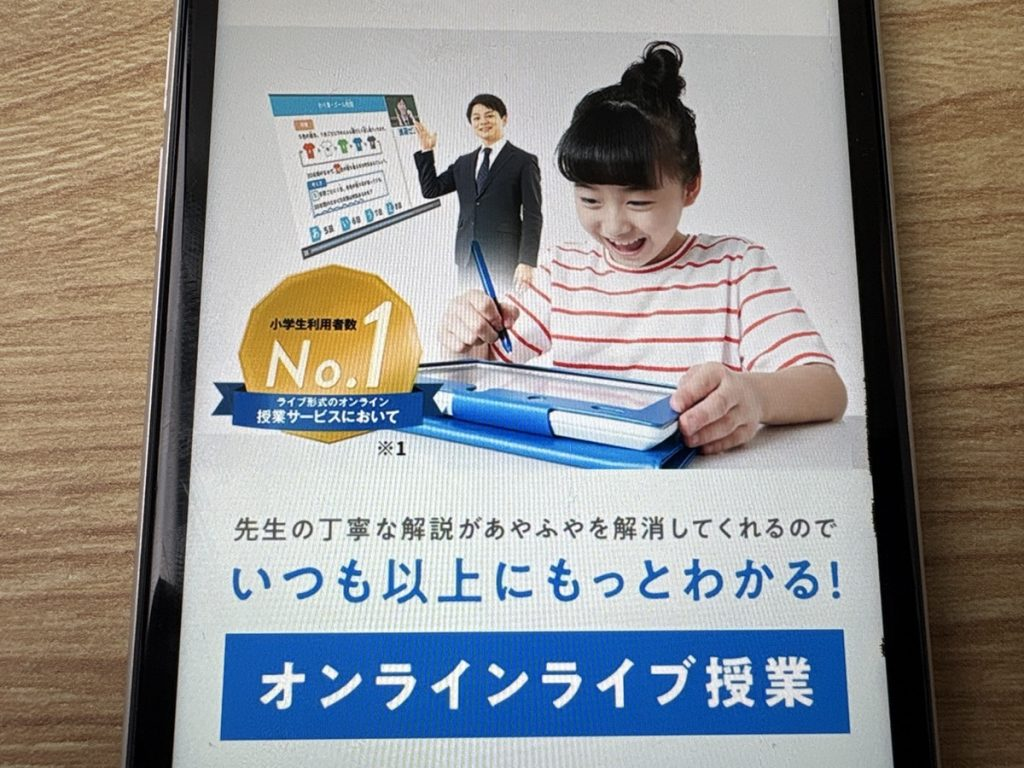
小学校の3段階通知表評価における「よくできる」の割合は、おおよそ20%が目安です。
現在では相対評価ではなく絶対評価になっているため、クラスや学校によっても数が異なる点は押さえておきましょう。
「よくできる」の数が少ないことが気になっている場合や、「もう少し」を減らしたいがどう学習すればよいかわからない場合は、通信教育などを活用します。
小学生が楽しみながら学習習慣をつけるなら、進研ゼミがおすすめです。
進研ゼミ小学講座は、タブレット端末を使い、個別カリキュラムで学習を進めます。
集中が続く7分設計のレッスンに、努力した分だけプレゼントがもらえるなど小学生のモチベーションが保ちやすいのが魅力です。
どこの通信講座を利用すればよいか迷っている方は、まずは無料の資料請求を行ってみてください。
2ヶ月だけの受講もOKなので、まずは有料教材を試してみたいという方にもおすすめです。
進研ゼミ小学講座の公式サイトをみる